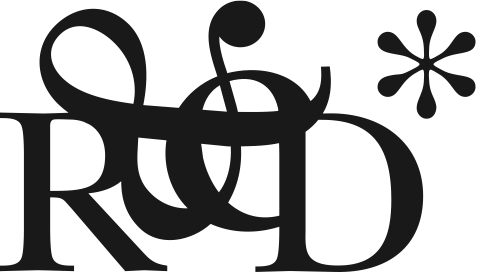文系卒がもっと必要である理由
筆者:クリスチャン・マスビアウおよびミッケル・B・ラスムッセン
質問:本稿は「文系卒はもっと必要か?」という疑問に対する回答である。
筆者について:クリスチャン・マスビアウおよびミッケル・B・ラスムッセンは、人間科学に基づく戦略革新コンサルティング企業「ReD Associates」のシニアパートナーであり、本稿は同氏らの意見をまとめたものである。
ここ数十年、人文科学を見下す傾向が妙に流行っている。現代の学生たちは、英文学の古典や20世紀の歴史、プライバシーの倫理を学ぶのは楽しいが無駄な贅沢だと言われ続けてきた。不足する教育資源を最優先に投じるべきは、数学や工学などの技術分野だという傾向がある。
しかし、この短期的な市場の原理が30数年もの長いキャリアを通して通用し続けることはないだろう。わずか一世代前、弁護士は投資銀行家よりも稼いでいた。だが今では法学部出身が飽和状態にあり (それでも法学専攻に投資する価値があるというデータはあるようだが)、一方の投資銀行は人材不足を嘆いている。このような事態を遠い未来に向けて予測することは基本的には不可能だ。
文系卒で成功を収めるのは難しいとも言われている。米ノースカロライナ州のパット・マクローリー知事(共和党)は、学生の就職率にどれだけ貢献しているかに応じて公立のコミュニティカレッジや大学に補助金を出すべきだと主張し、1月には次のように述べている。
「・・・率直に言って、ジェンダーの勉強をしたいのであれば、私立の学校で自由に勉強をすればいいと思います。でも卒業後に就職できないのなら補助金を出したいとは思いません・・・私たちが今必要としているのは技術職なのです。」
しかし、文系卒の中には、成功したキャリアを築き、その過程で膨大な雇用を生み出した人も多くいる。ビジネスインサイダーの報告によると、プロクター・アンド・ギャンブルのA・G・ラフリー(仏語および歴史) 、元マサチューセッツ州知事で共和党大統領候補のミット・ロムニー (英語)、ジョージ・ソロス (哲学) 、ディズニーのマイケル・アイズナー (英語・演劇)、ペイパルのピーター・ティール(哲学)、アメリカンエクスプレスのケネス・シェノルト(歴史)、カール・アイカーン(哲学)、元財務長官のヘンリー・ポールソン(英語)、最高裁判所判事のクラレンス・トーマス(英語) 、CNNのテッド・ターナー(歴史)、IBM元CEO サム・パルミサーノ(歴史)など、計30人のビジネス界の重鎮が名を連ねている。
シリコンバレーの中心地でテック企業を起業または経営する人の大半は、科学、技術、工学、数学 (STEM) 出身だろうと思う人もいるだろうが、実際は違う。ワシントン・ポスト紙のイノベーション欄のコラムニストで、スタンフォード大学のロックセンター・フォー・コーポレートガバナンス研究員でもあるヴヴェック・ワファによると、調査対象となったテクノロジー企業やエンジニアリング企業の創業者652人のうち、STEM分野で最終学歴を取得していたのは47%(そのうち37%がエンジニアリングまたはコンピュータ技術、2%が数学の学位)で、残りの学生は教養、医療、ビジネスの学位をうまく組み合わせて卒業していた。
こうした事実から非常に重要な疑問が浮き彫りになる-「製品や顧客という現実の世界で文系の学位は何の役に立つのか?」。その答えは、「大半の人が想像するより遥かに役に立つ」だ。「顧客を知ることはビジネスに有益か?」が問題の核心となるが、消費者の世界を深く理解し、彼らが見ているものを見て、彼らの行動の背景にある理由を理解するのは容易ではない。なかには飛び抜けて優れた直感を持つ人もいるが、顧客の心を奪おうとする大半のビジネスパーソンにとって地道な分析作業を避けて通ることはできない。
分析作業とは、人々の生活の全体像を理解する上で役立つデータを取得し、分析することを意味する。人を理解する上での現実的な問題は、細菌や数字の分析とは違い、調査されると人間は行動を変えてしまうという点だ。鳥や地質堆積物は、誰かが見ているからといって、急に自意識過剰になって行動を変えることはない。だが生きた人間を調査するときには、自然を調査する場合とは全く異なるアプローチが必要となる。顧客がどのような存在であるかを理解したければ、まず自分自身の人間性や経験に向き合う必要があるのだ。
このようなアプローチは人文学に見て取れる。例えば、作家デイヴィッド・フォスター・ウォレスの著書を学ぶと、自分の世界とは異なる世界に足を踏み入れて共感する方法を学ぶことが可能だ。神経をむき出しにして社会に批判的な視線を向ける彼の複雑な世界観は、市場調査の結果よりも、1990年代の若者として生きることについて多くを物語っている。さらに重要なのは、文章のニュアンスを汲み取れる読み手としてのスキルは、中国やアルゼンチンの自動車、石鹸、コンピュータの消費者を深く理解するための能力に通づるものがあるという点だ。他人やその習慣、状況を理解するという専門性の高いスキルなのである。
もちろん各市場の企業はこの重要性に気づいている。アメリカ大学協会のデボラ・ハンフリーは最近の調査で、雇用者の95%が「批判的思考を持ち、クリアな意思疎通が可能な上、複雑な問題の解決能力を備えていることは、志願者が大学で何を専攻したかよりも重要である」と回答していると述べている。これらは人文学で習得する最高峰のスキルである。
現在、インテル、マイクロソフト、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの最先端の企業を筆頭に、「顧客中心のマーケティング」 や「顧客の深い理解」 と称される大規模なイニシアチブが開始されている。こうしたプログラムの目的は、企業が顧客をより良く理解できるよう支援することだ。
問題となるのは、エンジニアやデザイナーの大半が、概して自分の好みに似た人のために製品を作っているという点だ。彼らには、ジャカルタに住む10代のインドネシア人が新しい携帯電話を手にすることがどういうことなのか、25歳のブラジル人がどんな飲み物を好み、必要としているのかを深く理解できるような人文学専攻のスキルは備わっていない。
文系卒は危機に陥ってはいない。競争力を強化し、製品やサービスを向上させるためには、今まで以上に文系卒が必要だ。貴重な金鉱はもう私たちの手の中にある。その実現のために企業が実施すべきは、ビジネスと人文学の2つの文化を融合することである。スタートとしては、企業と大学が研究調査で連携していくのが最適であろう。これは今後10年間、研究機関と企業の研究開発部門の双方が最重要課題として据えるべきことである。