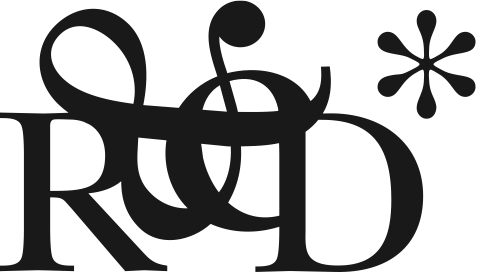シックデータの強み
製品やサービスが消費者の感情の動きに与える影響について知る必要性
筆者:クリスチャン・マスビアウおよびミッケル・B・ラスムッセン
本質的に、あらゆるビジネスは人間の行動を予測する(賭ける)ことで成り立っている。どの製品が最も売れそうなのか?どの従業員が最も成功しそうか?顧客はどのくらいの金額を支払う意思があるのか?こうした「賭け」を得意とする企業こそ市場で成功する傾向にあるのだ。
そのため、ビジネス界で最近流行っているのが「ビッグデータ」(強力なデータ分析ツールでふるいにかけた巨大なデータセット)であることに不思議はない。ビッグデータは、私たちの行動や嗜好に関わる情報収集に役立つ素晴らしいツールだが、「なぜ私たちが特定の行動を取るのか」という点について説明することはできない。
実際、ビッグデータの数字やグラフ、事実に頼りすぎる企業には、消費者の複雑で質的な日常生活の側面を度外視してしまうリスクがある。世界や自分たちのビジネスが今後どのように進化していくかを想像し、それを直感で捉える能力を失ってしまう危険性があるのだ。GPSの指示に従って初めて訪れた街の雰囲気やムードを見逃してしまうのと同じように、思考をビッグデータに委ねると、注意深く観察して世界を理解しようとする能力が衰えてしまう。
成功している企業や経営者は、消費者が製品やサービスに出逢うときの感情や直感を理解しようとするため、状況が変化しても速やかに適応できる。つまり「Thick Data(シックデータ)」 と呼ばれるインサイトを活用することができるのだ。
レゴ社の経験について紹介しよう。2004年、デンマークを拠点に置く同社は1日に100万ドルもの損失を出し、顧客との接点も途絶えて倒産の危機に瀕していた。
当時、社内には明確な打開策が提案されていた。現代の子どもたちは、「瞬時に惹きつけられるもの」 を遊びに求めているはずだと。欲しいのは手に取ってすぐに遊べるおもちゃで、古典的なレゴのように1つ1つ丁寧に組み立てなければならないものではない、同社はそう考えていた。
レゴはこの仮定に基づいて、アクションフィギュアなどの新たな玩具の開発を始めたが、新CEOに就任したヨルゲン・ヴィグ・クヌードストープは、その着眼点は間違っていると感じていた。子どもたちがなぜ、どのようにして遊ぶのかを根本的に理解する必要があると考えた同氏は、世界5都市のレゴ利用者の調査をするようReDに依頼。調査チームはフォーカスグループではなく、実際の環境で子どもたちと一緒に遊ぶために派遣されることとなった。
膨大な数の動画、何千もの写真や日記、何百もの遊びの中で完成した作品やその体験の記録などの研究成果物を収集、レゴはそれらを綿密にコーディングして地理や年齢に基づくパターンを模索。そうすることで、データの隅々からゆっくりとあるパターンが浮かび上がってきた。
判明したのは、すべての子どもがレゴのコアなファンではないが、ものづくりが好きな子どもたちは「遊びを通した体験」に対する熱意が高いということ。彼らはスキルの習得を目指していて、自分のレゴビルダーとしてのレベルを知りたいと思っている。この発見はチームにとって霧が晴れたような瞬間だった。結局のところ大切なのは、いまも変わらず「ブロックに立ち戻る」なのだ。
現在、レゴは再起を果たした企業だ。最近上映された映画「LEGOムービー」 の成功など、その復活には数多くの理由があるが、「遊びを通した体験」に対する理解を深めたことが1つの要因となったことに違いはない。
デンマークに拠点を置く医療技術会社コロプラストは、1954年の創業以来、毎年2桁成長を続けてきたが、2008年になると突然、全四半期で売上目標が未達成となった。結腸手術後に装着するストーマバッグのニッチ市場で長年の世界的リーダーであった同社であるが、競合他社に製品の市場シェアを奪われていたのだ。
当時、コロプラストの研究開発チームは、ストーマバッグの 「漏れ」 の問題を解決することに注力していた。漏れを体験した人は製品への信頼を失い、他の製品に乗り換えることを示した調査は無数にある。業界全体で前提となっていたのは、粘着剤が優れているほど漏れが少ないという考えだった。
コロプラストの技術者たちは何年もの間、製品に少しずつ改良を加え、新しい機能を追加し、粘着剤の改良を試みたが、こうした取り組みでは十分ではなかった。卓越した製品を届けるために何ができるかを理解するため、同社は顧客の日常生活に密着することを決断。数ヶ月にわたり、ReDとの連携で顧客の生活に関するシックデータを収集、分類、分析した。
動画や写真、そして患者の直の感想を検証していくうち、コロプラストの幹部たちは患者の実際の身体の様子や自社製品がどのように使用されているかを改めて確認することができた。「写真や日記を手に取り、ページをめくることで、顧客の体験を感じ取ることができました。他では得られない特殊なデータだと思います」とある幹部は話している。
こうした調査の結果、チームは問題が粘着剤ではないことに気付いた。おぞましい漏れを引き起こしていた原因は、多様に変化する患者の身体に、製品がうまくフィットしていないからであり、患者の多くは、術後に体重が大幅に増減したり、傷跡が残ったりしたことでストーマバッグの固定に苦労していたのだ。
コロプラストはこの知見に基づき、体型別に3つの製品カテゴリーを開発。これらの製品は漏れの問題の解決に役立っただけでなく、将来の革新に向けた明確な視点と方向性を打ち出すことにつながった。
最後に、サムスンのテレビ事業について取り上げてみる。2000年初頭、サムスンのテレビは棚に並んでいる他のテレビと同じような見た目だった。他社製品より目立った商品を打ち出したいと思ってはいたものの、同社幹部たちは消費者を夢中にさせる方法を見いだせずにいた。そこでサムスンは、「現代の家庭でテレビは何を意味するのか?」という、文化的背景を考慮した人間行動という大きな問いを投げかける必要があった。
ReDはサムスンとの連携でこの疑問に対する答えを導き出した。数百時間に及ぶインタビューや動画、その他の研究成果物を通じ、テレビ製品に係る重要なパターンを特定したのだ。インタビューでは、「テレビの見た目が気に入らなかったので隅に隠した」と答える人や、精巧に作られた椅子のように 「普遍的なデザイン」を求めている人もいた。つまり大半の回答者がテレビを電子機器ではなく家具として捉えていたのだ。
この本質的な知見から、同社チームは、不細工な機器から近代的な家具に近い美しさを目指して、製品を一から再設計することに成功した。スピーカーや他の目障りな備品を隠し、営業、マーケティング、サービスの手法も一変。こうして完成したテレビは、形状と機能が完璧に融合した「家具」として生まれ変わった。
シックデータを扱うのは容易ではないが、それを避ければ複雑なビジネスの問題を機械任せにする結果となってしまう。優れた計算能力を自由に駆使できるとしても、時には問題と向き合い、じっくりと辛抱強く人間観察をして問題を解決する以外に選択肢がないこともあるのだ。
コンサルティング会社「ReD Associates」のマスビアウ氏およびラスムッセン氏は、本稿の元となった「The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Toughest Business Problems (なぜデータ主義は失敗するのか?:人文科学的思考のすすめ)」の著者である。