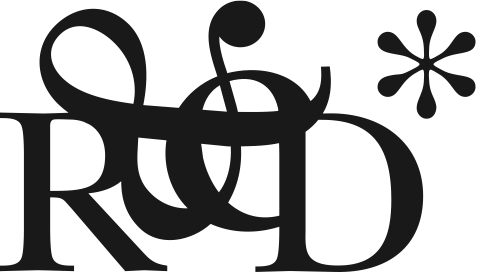人類学者がバーの売上に貢献
筆者:クリスチャン・マスビアウおよびミッケル・B・ラスムッセン
概要:「ビアコ社」がパブの売上減に気づいたとき、市場調査や競合分析は何の助けにもならなかった。そこで、調査のために社会人類学者のチームを派遣。結果として得られた調査記録、写真、動画などのデータは、同社の販促品と研修方法の刷新を促す洞察をもたらした。売上高は2年以内に回復し、現在も増加を続けている。
ビアコ社の体験談は、「センスメイキング」という新しいアプローチがいかに顧客の真のニーズを明らかにし、製品開発、組織文化、企業戦略の変革を成功に導くかを示している。人類学、社会学、政治学、哲学といった人間科学に根ざしたセンスメイキングは5つのステップで構成される。企業は次の事項を実践する必要がある。
経営課題を別の視点から捉え直し、顧客の製品・市場体験に焦点を当てる
生データを直に入手する
データのパターンを探る
新たな知見を生成する
知見をイニシアチブに落とし込む
センスメイキングは、ビジネスで最も困難とされている問題の解決に貢献するもので、リーダーは自分たちが従事するビジネスの真の姿について創造的に思考を巡らすことができる。
2006年、ヨーロッパの大手醸造会社である「ビアコ社」は、バーやパブの売上減少に直面しており、市場調査や競合分析といった強固な取り組みにもかかわらず、その原因を特定できずにいた。主力商品の定番ラガーが好評で店舗販売は右肩上がりだったが、バーでは手応えがなく、積極的なプロモーション活動も役に立たなかった。いったい何が間違っていたのか?
従来の調査方法では打つ手がなくなった同社は、社会人類学者のチームにイギリスとフィンランドの10数軒のバーを訪問して調査を実施するよう依頼。人類学者たちは、ボルネオ島の見慣れない部族を研究するかのようにプロジェクトに取り組んだ。彼らはバーに入り浸り、何か見つかるかもしれないという仮説もなく、ただオーナー、スタッフ、常連客を観察し続けた。その結果得られたのは、150時間にも及ぶ観察動画、数千枚の静止写真、数百ページの調査記録の数々。同社のマネージャーチームは数週間をかけて人類学者たちと生データを精査してパターンを模索した。
結果、徐々にパターンが浮かび上がってきた。同社は、バーのオーナーがコースターやステッカー、Tシャツなどの販促品を重視していると考えていたが、実際にはあまり使われておらず、最悪のケースでは物笑いの対象になっていた(あるバーでは、「ガラクタ箱」とラベルが貼られた箱に詰め込まれていた)。また、女性のウェイトレスが今の仕事から抜け出せず、客に色目を使うフリをする「短パン女」の役回りを強いられていることに苛立ちを感じていることも分かった。さらに彼らは主要な販売チャネルであるにもかかわらず、同社の製品についてほとんど知らず、知ろうともしていなかった。
これらの発見に基づき、ビアコ社はパブやバーに対するアプローチを一新。画一的な販促物を投入するのではなく、バーやオーナーのタイプに合わせた物品のカスタマイズを開始した。さらにバーのオーナーを正しく理解するための研修を営業部員に提供し、販促キャンペーンの企画に役立つツールを開発。さらにホールスタッフにブランド研修を行うための「アカデミー」を店舗内で実施し、遅くまで働く従業員のためにタクシーサービスを提供することで女性従業員からの支持を得た。2年後、ビアコ社のパブとバーの売上は回復し、売上と市場シェアは成長を続けている。
ビジネス界では、人類学、社会学、政治学、哲学といった人間科学を学術界と結びつけて考える人が多いが、それには正当な理由がある。こうした学問の研究結果は理解が難しく、その知見はビジネス界では実用的でないと考えられることが多いのだ。
しかし、こうした見方は急速に変化してきた。最近の手法からも、企業が人間科学を活用する方法が飛躍的に構築されてきている。この斬新なアプローチは、インテル、IBM、サムスンなどのテクノロジー企業の研究部門、アディダス、レゴ、プロクター・アンド・ギャンブルなどの大手消費財メーカーのマーケティング部門、ノボ ノルディスクやファイザーなどの世界的な製薬企業、ビジネスリーダーの思考や執筆作業、そして私たちのようにハードサイエンスとソフトサイエンスを融合させた新しい種類のコンサルタント企業でも続々と採用されている。
IBMが1,500人のCEOを対象に行った最近のグローバル調査によると、CEOが直面する最大の課題は、いわゆる「複雑化のギャップ(complexity gap)」だということが明らかになっている。回答者10人のうち8人は、ビジネス環境が複雑化すると予測しているが、こうした変化に対する準備は万全だと感じている人は半数に満たなかった。また、この調査では、CEOが複雑化への対応における最大の欠点は顧客インサイトの欠如だと考えていることも明らかになっている。彼らは顧客インサイトの入手を他の意思決定タスクよりも遥かに重要視しており、「顧客志向」はリーダーにとって最も重要な特性だと位置づけている。
そのため、多くの企業がビッグデータやアナリティクスを活用した顧客調査に注目している。こうしたアプローチでは、市場の部分的な側面について驚くほど詳細なデータを入手することができるが、それは全体像とは程遠く、しばしば誤解を生むこともある。顧客が次に何をクリックして購入するのか予測するのは可能かもしれないが、その行動を裏付ける動機は定量的なデータで把握することはできない。こうした本質を見抜く力がなければ、企業は複雑化のギャップを埋めることはできないだろう。
消費者を「1」と「0」の羅列として捉えるあまり、マーケターやストラテジストは人間的な要素を見落としてきた。結局のところ消費者は人間である。人間は不合理なときもあり、自分でもよく分からない理由で行動してしまうこともある。しかし、ほとんどのマーケターは、企業文化、マネージャーの偏見、そして(最近増えている)膨大だが不完全なデータの流れで形成された顧客行動に関する思い込みに囚われているのだ。
人間科学を採用したアプローチは、従来とは根本的に異なる顧客理解の手法だ。それにはまず、私生活と社会的、文化的、物理的な世界が複雑に相互作用する人間行動の根源について調べていく必要がある。従来型のビジネスツールでは見逃されてきた知見を掘り起こす作業となる。この非線形プロセスは「センスメイキング」と呼ばれるもので、消費者の行動に影響を与える微細かつ無意識な動機を明らかにし、製品開発、企業文化、さらには企業戦略に変革をもたらす知見を与えてくれる。以下に説明していくように、センスメイキングと人間科学のツールは、新たな地域市場や新たな世代の消費者など、馴染みのない社会的・文化的状況下で生じた新たな問題(つまり、「大きな未知」)に企業が対処しようとする際に最大の力を発揮する。または、今の市場や消費者が予想外の行動を取り始めた場合にも、その解明に大きく役立つ可能性がある。(サイドバー「大きな未知を特定する方法」を参照)
-
ビジネス関連の問題の多くは技術的に複雑なものだが、マネージャーはそれらを完全に理解し、問題解決にどのようなデータが必要かを把握し、前進に向けた明確なプロセスを備えている。対照的に、「大きな未知」は彼らに馴染みのないビジネス上の課題だ。特定の問題、市場、顧客に慣れていなければ慣れていないほど、従来の調査手段の関連性は低くなり、人間科学とセンスメイキングの関連性が高くなる。
センスメイキングは、新たな地域的市場や新たな世代の消費者など、馴染みのない社会的・文化的背景を理解したい場合や、現在の顧客に関する思い込みが事業を誤った方向に導いていると感じたときにその真価を発揮するプロセスだ。
ビジネス上の問題を3つのカテゴリに分類した以下の診断方法は、企業が直面している問題のタイプを特定し、センスメイキングを適用できるか否かを判断するのに役立つ。マネージャーは、レベル3の問題(大きな未知)をレベル2の問題(仮説)と勘違いしていることが多く、その結果、必要なときにセンスメイキング・ツールを使用していないケースがある。
レベル1:既知
顧客と市場に関して精通している
将来の明確な見通しが立っている
ビジネス上の問題をしっかり把握している
従来のデータや分析手法で問題を解決できる
例:天候が理由で来店客数が少ないため、ホリデーシーズンの売上が目標を下回っている。テレビ広告をX倍に増やし、Y倍に値引きすれば、売り上げは回復するだろう。
レベル2:仮説
顧客と市場に関してある程度の理解がある
様々な結果を想定することができる
以前に同じ問題に遭遇したことがあり、感覚的に問題を把握できる
仮説を立ててテストしてみることができる
問題解決に必要なデータソースや分析モデルに慣れている
例:販売員数を増やしたにもかかわらず、1店舗当たりの売上が減少している。考えられる理由がいくつかあり、テストする方法を思いつくことができる。
レベル3:大きな未知
顧客や市場について全く慣れていない
想定される結果をほとんど予測できない
このような問題に遭遇したことがない
テストできる仮説がない
通常のデータソースや分析手法では、明らかに問題解決に役立たない
例:アイデア考案から開発までのプロセスは充実しているが、発売後に成長が生まれていない。
センスメイキングの実践
センスメイキングの中核にあるのは、人々がどのように日々の生活を体験しているかを研究する現象学の実践である。スターバックスを例に上げると、経済学では1日に何杯のコーヒーが売れるかを予測できるが、現象学では顧客がコーヒー体験をどのように認知しているかを解明することができるのである。スターバックスがコーヒーの現象学に関する知識を活用していることは有名で、コーヒー自体の提供とは一線を画し、繊細かつ複雑なスターバックス体験(素敵なバリスタ、在宅勤務者の居場所、厳選されたBGMなど)に顧客がプレミアムを支払うことで収益を上げている。
次に、レゴグループがどのように現象学を使って顧客の深層心理にある動機を理解したかを考えてみよう。8年前、同社はコアなレゴファンとの接点を失うことで大きな損失を出していた。しかし現在、センスメイキングの活用もあり驚異的な業績回復を果たして、世界で最も尊敬される最大手玩具メーカーとなった。
レゴファンの子どもたちやその親がレゴで遊ぶときに何を求めているのかという顧客理解の姿勢よりも、ブランド力で新市場に進出しようとする決断を優先したことで負のスパイラルに拍車がかかった。日々の生活に忙しく、スピード感のあるデジタルゲームを手に取りがちな子どもたちには、昔ながらのプラスチック製のブロックを組み立てる時間も根気もないだろう、と考えたレゴ社は、この誤った思い込みからアクションフィギュアやビデオゲームの開発に着手。遊びにかける時間や創造力をあまり必要としないスタイリッシュで斬新な見た目の玩具を作るようになった。同時に親たちがレゴに抱くノスタルジックな感情も失われ始め、「ブロックを買いたい」という衝動も消えていった。
レゴが顧客との繋がりを失っており、新製品は解決策にならないと悟ったヨルゲン・ヴィグ・クヌードストープ元CEOは、「遊びの現象」を深く理解する必要があることに気付いた。子どもたちが遊ぶときにどんな体験をするのか?そこから何を求めているのか?レゴはそのニーズにどう応えることができるのか?
それを確かめるために、同社は米国とドイツの家庭に調査員を派遣。彼らは数カ月かけてデータを収集し、親子と面談を行い、写真やビデオ日記を作成し、家族と買い物をし、おもちゃ屋の調査を行った。このようにして膨大なデータを蓄積していったのである。同社チームが収集されたデータを入念に調べていくうちに重要な知見が浮き彫りになってきた。とりわけ目立った発見は、子供たちが過密なスケジュールから逃れるため、そしてレゴのスキルを習得するために遊んでいるという事実だった。こうした知見から、日常生活が忙しすぎて子どもたちがレゴに夢中になれないのだ、という思い込みは誤ったものだということが明らかとなった。実際のところ、レゴを組み立てて遊びたい、その時間もある、もっと上手くなりたいと思っている子どもたちは存在するのだ。
レゴの新事業グループ責任者だったパール・スミス・メイヤーは、「今、レゴであることを誇りに思うような製品を作っています。箱を見ればレゴだとすぐにわかる、そんな商品です。誰かにブロック遊びを無理強いすることはできません。調査を通して、誰のために商品を作りたいかを決断することができ、『本来のレゴが好きな人のためにレゴを作り始める』というキャッチフレーズも誕生しました」と述べる。
これは、市場データ分析、コンジョイント分析、調査、フォーカスグループなどの従来の戦略プロセスでは見落とされていた(そしておそらく入手できなかった)画期的な知見であった。
センスメイキング・プロセス
センスメイキングの各段階を説明するために、全くタイプの異なる会社、デンマークの医療技術会社を見てみる。コロプラストは、胃や腸のがん患者に施される人工肛門造設術から回復中の妹を看病していた看護師エリーゼ・ソーレンセンの着想をきっかけに、1954年に誕生した会社である。人工肛門造設は命を救う処置ではあったが、エリーゼの妹は、ストーマ(排泄物の出口となる穴)を恥じて社会的に孤立してしまった。自作のストーマバッグ(当時はそれしかなかった)が漏れることを恐れ、外出するのが億劫になってしまったのだ。エリーゼが身体に固定する粘着性リング付きのストーマバッグを考案したことで同社の事業が立ち上げられた。
50年後、コロプラストは欧州市場をリードする医療用装具会社となり、同業界では世界で最も患者志向の企業として患者からも高く評価されている。しかし2008年、同社の最大部門であるストーマケア部門は、イノベーションと営業に多額の投資をしていたにもかかわらず業績停滞を経験していた。
同社は先進的な研究開発で有名で、リードユーザー研究、ユーザー共創、デザイン思考研修、NPV計算など、イノベーションで主流のトレンドはすべて実践してきた。しかし製品パイプラインの充実とは裏腹に売上には勢いがなく、その原因は謎に包まれていた。フォーカスグループや大規模な定量調査でストーマ患者が体験する不快感の多くが明らかとなり、それらに対処するために多数の製品アイデア(バッグ装着時のロック機構や粘着剤の改良、新しいフィルター、新素材の採用など)も採用してきた。しかし、これらのイノベーションはいずれも成長の牽引につながるものではなかった。
コロプラスト経営陣は、ストーマ市場に関する基本的な前提、つまりコロプラストを長年にわたり成功に導いてきた考え方に誤りがあるに違いないということに気づいた。まさに「大きな未知」に直面した瞬間であった。どうすれば新たな成長の源泉を見つけられるのか?その答えを提供してくれたのは、5段階のセンスメイキング・プロセスだった。
-
「人間科学者」は、人間が日々の生活をどのように体験するかを調べる現象学に基づいて研究を行っている。その目標は、人々が周囲の環境と関わり合う複雑かつ微妙な、そして時として無意識な手段を解明することである。
料理人が厨房、他のキッチンスタッフ、ウェイター、料理、客、その場にある他の無数の要素とどのように関わっているかを考えてみよう。それらの動きの大半は無意識に行われている。右手で冷蔵庫を開け、ウェイターには特定の口調で怒鳴り、キッチンスタッフには別の口調を使う。肉にかけるコショウの量は計測しないが正確な量を知っている。小指でソースを味見し、何が足りないかを瞬時に把握する。こうした一瞬一瞬の行動を正確に説明することなど本人にはできないだろう。そこにあるパターンを見つけるには、相手を近くから観察しなければならない。
仮にあなたがレストランに備品を供給をするビジネスをしており、なぜか売り上げが落ちているとしたら、料理人にこの商品とあの商品のどちらが好きかと聞いても、おそらく具体的な答えは返ってこないだろう。しかし問題を現象として捉えて、「料理人にとって調理するとはどんな意味を持つのか?」と考えれば、相手の真のニーズを理解できる可能性が高くなる。
ビジネス上の問題の大半は「現象」として捉え直すことができる。そのコツは、視点をインサイドアウト(企業が問題をどのように認識するか)からアウトサイドイン(顧客が問題をどのように認識するか)に転換することだ。
例:
ビジネス上の問題:銀行はどのようにして解約を減らすことができるか?
現象:銀行での顧客体験はどのようなもので、なぜ顧客離れがあるのか?
ビジネス上の問題:コーヒー事業でプレミアムサービスを届けるにはどうすればいいか?
現象:素晴らしいコーヒー体験とは?
ビジネス上の問題:中国における玩具の市場進出戦略はどうあるべきか?
現象:中国における遊びの役割とは?
このように 、コロプラストは「どのようにして新たな成長の源を手に入れるか?」という問いを、「ストーマを装着して生活するとはどのようなことか?」という問いに転換。同社のマネージャーは、誰がいつどの製品をどれだけ購入したかなど、顧客データについて多くのことを知っていたが、顧客の実生活についてはあまり把握していないことに気づいた。ストーマ患者になるとはどういうことなのか?自分に対して抱くイメージにどのような影響を与えるのか?社会生活への影響は?調子の良い日や悪い日とはどんな日なのか?
コロプラストの従来の製品開発とマーケティング戦略は、顧客とそのニーズに関する2つの前提に基づいて推進されていた。1つ目は、患者は退院後2年以内にストーマケアに慣れて通常の生活に戻れるということ。そして2つ目は、製品開発はストーマバッグの多様な機能を1つずつ改善していくことに焦点を当てるべきということである。
これらの仮定には明らかな問題があるようだった。一体何が間違っていたのか?
データの収集
センスメイキングのプロセスにおけるデータ収集は、これまでの前提を疑うよう設計されているため、従来の分析や研究のアプローチとは根本的に異なる。仮説に基づいた調査を実施したり、ビッグデータを分析したり、綿密にシナリオ化されたフォーカスグループを実施したりするのではなく、研究者が被験者の生活に関与していくものだ。重要なのは、仮説を立てずに調査に取り組み、何が見つかるかという先入観を持たずにオープンエンドな方法で大量の情報を収集すること。このような偏見のないデータ収集によってのみ、顧客の真の体験を探ることができる。
結果として得られるデータセットは、市場調査ツールの大半で生成されるような現実を歪めた情報ではなく、直接的に入手された個人的な生データである。これらの驚くべき情報は、セグメント、ニーズ、消費機会といった抽象的なデータで顧客を捉えることに慣れているビジネスリーダーに多大な感銘を与えるものとなりうる。
セグメント、ニーズ、消費機会といった抽象的なデータで顧客を捉えることに慣れているビジネスリーダーに多大な感銘を与えるものとなりうる。
同社マーケティング部門シニアバイスプレジデントを務めていたクリスチャン・ヴィーラムセンの指揮の下、社会科学調査員が世界中に派遣され、友人や家族との時間、外出時、そして(おそらく最も重要な点だが)不安や恥ずかしさで家に閉じこもっている時など、2日間にわたってストーマ造設患者の様子を観察した。さらに、ストーマケア看護師と1日を過ごし、患者に合わせた製品の選び方、患者の退院準備、患者の自宅ケアに関する懸念点を理解するよう努めた。これらの生データは、慎重に整理した動画、日記、写真、調査記録、パンフレットや梱包等の資材の形式でコロプラストに提出された。
オープンエンドのデータ収集は膨大な範囲を対象にしたものだが、調査設計に優れた科学者の監督を要する統制の取れた体系的なプロセスである。基本的には、現象(つまり、調査対象の体験)に根付く主なテーマを特定し、それぞれを一連の質問に落とし込んでいく必要がある。
ストーマ患者の日常的な体験という現象は、以下のようなテーマに落とし込むことができる。
ストーマは日常生活にどのような影響を与えるのか?
患者はどのようにして日々の計画を立てているのか?
患者、看護師、医師にとって質の高いケアとはどのようなものか?
ケアに対する患者と介護者の要望は?
患者の日常的なケアとはどのようなものか?
患者にとって重大なニーズや問題は何か?
製品や備品を選択する際に大事な意思決定の手順は?
指針となる一連の質問が決まれば、直接的な観察、被験者の活動への参加、深層面接、集団面接、動画撮影など、関連データを集める上での最も効果的な手段を決定するのは比較的に簡単だ。他の分析プロセスと同じく、データの収集と構造化は、各ルートで入手される情報間の比較を容易にするものでなければならない。また、入手媒体の種類、地域、調査対象者に応じて情報をコード化するなど、検索と共有の簡素化を目的にデータを整理して保存する必要がある。
パターンを探す
データ収集段階の終わりに、同社チームは2,000枚の写真、数百ページの調査記録と面談内容、2ギガバイトの動画で構成されるデータベースを手に入れた。だが、もちろん分析なしでは、データ収集は単なる報告で終わってしまう。
そのため、チームはデータを構造化し、すべての被験者の生活を詳しく検証した上で、全体的なテーマや共通項(漏れを避けるための方法や、家庭、職場、趣味の場等でのケアなど)を探った。このように点と点をつなぐことで、あるパターンを浮上させることができたのだ。
パターンを明らかにする鍵は根本原因を見つけることにある。そのため今回のケースでは、患者と看護師の行動を根本的に解明する必要があった。これは玉ねぎの皮をむく作業に似ている。外側の層には、患者がどのくらいの頻度でバッグを交換するか、その際にどのような不便を感じるかなど、実際に観察可能な事実が含まれる。その次の層では、患者の行動や選択の表れである習慣や慣行が伺える。そして最終的な核を構成するのは、これらの習慣や慣行の根本的な原因である。
こうした内側の層に埋め込まれた知見は直接的に入手することはできない。観察を通したパターンとして浮き彫りになるものだ。コロプラストの調査チームはこの深層分析を行うため、慢性的な障害が患者のアイデンティティに与える影響、社会的スティグマが高まる様子、ストーマケア、性生活、信頼性の役割について、さまざまな社会科学の理論を適用していった。これによって、患者が外出を避ける理由は社会的スティグマによって説明できるのか?自宅か出先かで患者のケアの基準に違いが生じるのか?患者の性生活にどのような影響が与えるのか?退院後の慢性患者のアイデンティティには変化が生じるのか?など、多様な角度からデータを検証することが可能となる。
ヴィーラムセンのチームは訓練を受けた研究者とともに、収集したデータと被験者の生活を深く検証していった。恋人との関係では単にフラストレーションを感じる人がいる一方、恥ずかしさや気まずさを感じる人もいた。結婚式や会議、授業中などにストーマバッグが漏れた恐怖の瞬間について話してくれた患者もいた。
「ストーマを装着して生活するとはどんな体験なのか?」という現象に何度も立ち戻ったコロプラストは、病院でのケアと自宅でのケアの相違が生む影響の重大さを把握し始めた。患者が入院しているときは横になっていることが多く、専門家に囲まれており、癌で体重が標準を下回ることがあり、大半の時間はストーマケアに費やされる。しかし、それがもたらす影響について気づかれることはなかったのである。通常、患者が退院すると専門家の介助はなく、自分の体がどれほど変わったかという問題と向き合わなければならない。傷跡が残った人、体重が減って皮膚がたるんだ人、急激に体重が戻って肥満になった人、退院後にヘルニアを発症した人も少なくない。入院中の決まった処置やルーチンは、時間が経つにつれて自宅では意味をなさなくなってくる。病院で看護師と一緒に選んだ製品は体に合わなくなり、ケアが複雑になって、漏れの問題も徐々に発生する。
コロプラストは、ほぼ解決済みと確信していた問題(漏れ)が、患者の人生を変える大変な問題として持続している事実にやっと気づいた。従来の調査結果を誤って解釈し、時間が経てば患者から漏れの苦情も出なくなるため、問題はもはや存在しないと考えていたのである。パターン認識の過程で明らかになったのは、苦情が減ったのは問題が解決されたからではなく、漏れのリスクを避けようと患者が生活習慣を根本的に変えていたからだった。ある患者の言葉を借りれば、「こんなものなんだろう」と退院後の生活を受け入れてしまっていたのだ。
実際のところ、患者が繰り返し体験する悲しいパターンは次のようなものである。術後のショックを体験した後、日常生活に戻るのは難しいが、夕食に出かけたり、映画に行ったり、友人に会ったりして社会生活を再開しようとする。だが、公共の場で最初の漏れを体験した後、漏れに対処できる場所の確保を最優先して行動範囲の見直しを始める。行ったことのない場所や遠出はやめ、慣れた場所に行動を限定。また何度か漏れがあったことをきっかけに生活をさらに制限する。レストランやその他のリスクの高い場所には行かなくなる。このようにして2年以内に多くの人がまったく外出しなくなったのである。このようにして、漏れの問題はある程度は制御できていたが(そのため漏れの苦情はあまり出なかった)、その過程で患者は人生の豊かさを失ってしまった。
主要な知見の作成
漏れの問題が継続しており、患者の生活の質に多大な影響を与えていることを知った同社マネージャーは、ポリマーと粘着技術に焦点を当てた同社のイノベーションが顧客の主要な問題をほぼ解決した、という同事業のコアとなる前提を根本から見直すことにした。
新たな視点でデータ検証を始めた研究チームは「何を見落としていたのか?」と問いかけて、業界の思い込みと患者の体験の間にあるギャップを模索した。そしてデータを精査していくうちに、あるパターンが浮かび上がってきた。面談や動画で多くの看護師が「画一的な身体はないから完璧な製品も存在しない」「良い製品だが誰にでも合うわけではない」と言っていたのである。同時に、バッグの固定に苦労しているという患者の意見も見受けられた。どんなに高性能なポリマーや粘着剤を使っても、患者の多くが信頼できるフィット感を得ることはできていなかった。彼らはリング等の付属品、ペースト、特殊な粘着剤、皮膚を漏れから守るクリームなど、多種多様な自作のソリューションも試していた。
研究チームがデータを調べていくうちに、「ストーマ患者の身体は多様であるため、画一的な解決策は存在しない」という現状を打破する知見が明らかとなった。主な問題は、患者のストーマのタイプではなく、患者の体のタイプだったのだ。当然のことのように思えるかもしれないが、独自のイノベーションプロセスを過信するあまり、経営陣や研究開発エンジニアはその可能性を見落としていた。個人が確証バイアス(現状を裏付ける情報のみを反射的に求めること)に惑わされることがあるように、組織全体もその影響を受けることがあるのだ。
個人が確証バイアス(現状を裏付ける情報のみを反射的に求めること)に惑わされることがあるように、組織全体もその影響を受けることがあるのだ。
コロプラストの粘着剤は、均一的な健康体には完全にフィットするようできていた。しかし、手術による傷跡や隆起、癌による体重の変化など、体に様々な変化が起こることでストーマのフィット感は大きく損なわれてしまう。
これほど大きな問題にもかかわらず、10億ドル規模の業界でこの問題に取り組んでいる企業は一社もなかった。コロプラストは、体型を分類化し、それぞれに合わせた製品を開発する必要があると即決。コロプラストも競合他社もこの開発には全く取り組んでいなかったため、その事業は絶大な可能性を秘めていた。
ビジネスインパクトの構築
もちろん、知見はイニシアチブに転換しなければならない。第1段階から第4段階まではセンスメイキングの手順で経営幹部にとっては比較的に新しい試みだが、最後のステップはビジネスリーダーに馴染みのイノベーション戦略の構築である。
コロプラストは、何千人もの顧客にさまざまな姿勢の写真を投稿してもらい、それらを参考に4つの基本的な体型を特定。「本当のカラダにフィットする」研究は、同社の全事業部にダイレクトな影響を与え、研究開発部門は新技術の開発、製造部門は新ツールの開発、マーケティング部門は説得力のあるストーリーの作成、営業部は新しいタイプの製品の販売、カスタマーサービス部門は患者サポートシステムの構築を実施する必要があった。
2010年に発売された「ボディフィット」製品は、患者のための解決策としても業績面でも大成功を収めている。これまでの2つの製品ファミリーは商業目標を達成しており、2014年には新製品が発売される予定である。コロプラストのストーマケア事業は、ストーマ製品市場全体を上回る勢いで成長を続けている。
「ボディフィット」プロジェクトは、他部門の同様の取り組みとともに、企業文化の活性化にも貢献している。会社が技術中心から顧客中心への転換を果たし、新製品が顧客の生活と会社の運命に多大な影響を与えたことで、研究開発部から営業部に至るまでの社員が新たな目的意識と革新的な精神を持つようになった。企業は長きにわたり、市場調査にエスノグラフィック・ツールを使用してきたが、センスメイキングによる革新は、研究技術よりも人間科学に基づく分析に焦点を置いたものだ。ビジネス上の最も困難な問題の解決に役立つ(新たな成長源の発見、新市場での勝利、企業文化の変容など)ことを知った世界中の企業は、センスメイキングの活用に着手し始めている。センスメイキングは、従来のツールでは見つからない答えを明らかにし、経営陣が自らの事業のあり方について創造的な視点を持つことを可能にしてくれる。
クリスチャン・マスビアウは、革新&戦略コンサルタント会社「ReD Associates」の顧客関係部門ディレクターで、ミッケル・B・ラスムッセンは欧州部門ディレクターである。両者は、本稿の元となった「The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Tough Business Problems(なぜデータ主義は失敗するのか?:人文科学的思考のすすめ)」(ハーバード・ビジネス・レビュー・プレス 2014年)の共著者である。
ミッケル・B・ラスムッセンは、Red欧州部門ディレクターで、「The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Tough Business Problems(なぜデータ主義は失敗するのか?:人文科学的思考のすすめ)」(ハーバード・ビジネス・レビュー・プレス2014年)の共著者である。