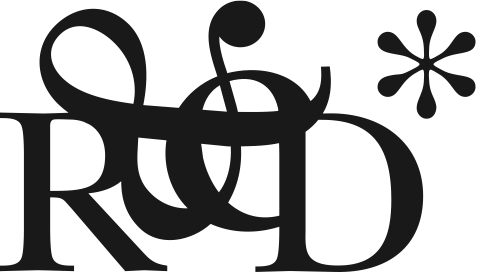「帰属意識(Belonging)」とは何か?
マリア・カリーとミッケル・クレンチェルが帰属意識に関する特別シリーズについてご紹介します。
「帰属(Belonging)」という単語は名詞や動詞として使用されますが、これは簡単に理解したり、個人が一人で実現できる人間の現象ではありません。帰属は与えられ、感じられ、評価され、肯定され、否定されるものです。他の人々や場所、物との関わり合いが必要であるため、個人を超えた社会的な広がりが実現します。入ってくるものと、出ていくものという「輪郭」に着目することで帰属領域を認識しやすくなるでしょう。コンサート会場で観客が一体となって歌ったり、スタジアムで他のファンと一緒にウェーブをしたりなど、強い感情が湧き上がったときに帰属意識を強く感じることができます。
対象的に、他の人が「集団に属している」と感じているのに自分は感じないという場合にも、帰属関係を意識することになります。例えば、誕生日パーティーに招待されなかったとき、その場にいた全員が他の候補者に投票したことに気づいたとき、見知らぬ人に「よそ者は帰れ」と言われたときなどです。それでも私たちはいつも帰属を話題にしています。ロックダウン後の状況をどう捉えるべきか、世界が身近になった現代にてインクルーシブな組織をどのように構築していくか、気候変動の解決に向けたコミュニティの団結をどのように達成するかといった問題について話すとき、私たちが本当に話しているのは帰属意識であり、それをいかに上手く実現するかが重要なのです。帰属とは、実際にはどのようなもので、どのように形成されるのでしょうか?すべてが善良なものでしょうか?何によって壊されるのでしょうか?どのように変化し、今後はどうなっていくのでしょうか?
「帰属(Belonging)」は、ReDが実施する研究で何度も登場するトピックです。新規のものから確立されたもの、一時的なものから長期的なものなど、コミュニティでの帰属現象に直接的または間接的に着目した研究を過去2年間で10件以上実施してきました。
あらゆる状況における帰属について深く理解するため、今回の特別シリーズではエッセイ、インタビュー、映画、写真を集約して私たちの思考をまとめてみました。地域社会とビジネスにとって重要であると考える本トピックについて好奇心を持って熟考することがその目標です。あらゆるブランド、製品、サービス、物理的空間または仮想空間は、帰属意識を創出することも、崩壊することも可能だからです。
現代における危機
人と繋がり合うことがかつてないほど簡単になった現代、その一方で自分の居場所を感じることが難しくなっています。学校や政府といった伝統的な制度に対する不信感の高まり、政治の分裂、地域コミュニティや共有空間の減少など、社会構造にほころびが生じているのです。孤独感の高まりや政治の二極化など、過去数十年にわたって報告されてきた問題も多く、パンデミックによって状況は悪化の途を辿りました。その一方で、遠くに住む人とオンラインで繋がったり、互いが都合の良いタイミング(非同期)でコミュニケーションを取ったり、普段の生活では出会わないような人と知り合ったりなど、物理的な空間や時間、さらにはアイデンティティに係るギャップの解消が可能な時代となりました。こうした2つの相反する現象(社会構造の衰退および人とかつてないほど繋がれる能力)が同時に発生しており、その狭間で「帰属」は板挟みの状態になっています。帰属は、私たちの生活の一部で欠けているから他のもので満たせる、というものではないからです。
「帰属」するということの意味
研究者である私たちが「帰属」と言うとき、それは他の個人のみならず、グループやコミュニティとの間にある受け入れや繋がりの心、安心感やお互い様といった感覚を意味します。帰属とは、知り合いやグループの一員であることと同じではありません。帰属意識がなくてもコミュニティの一員になることはできます。グループやコミュニティには、受け継がれたもの、選ばれたもの、一時的なもの、獲得したもの、閉鎖的または開放的なもの、オンラインまたは現実のものなど多様な形式があります。コミュニティで名前を知っている人もいれば、誰だか分からないけどそこに居るのは分かるという程度という場合もあります。
帰属意識は単一の形式を取るものではありません。日常生活で私たちが関わるグループやコミュニティから生じる多様な関係性が帰属意識をもたらしてくれます。帰属意識のなかには、時間をかけて親密な関係を育んでいくものや、関係が生じやすいが、すぐに消失してしまうような一時的なもの(日常生活の中で出会う人との弱い繋がりなど)もあります。私たちが帰属意識を感じるのは、過去の思い出を共有したり、教会や学校、住んでいる地区や国など、同じ文化風習に従っているからかもしれません。たとえ会ったことや一緒に活動したことがなくても、趣味が同じという理由だけで仲間だと感じる場合もあるでしょう。これは、暗号通貨などの分散型社会や、急速に拡大しているWeb3空間によく見られる現象です。
こうした区別が重要なのは、帰属意識のタイプによって、スキルアップや昇進に向けた人脈や知識の構築、または自分自身をさらけだしたり、新しいことを試したり、他者と協力できたりする空間など、私たちの生活に様々な利点をもたらしてくれるからです。こうした利点を組み合わせることで、急速に変化する不安定な世界の中で私たちは安定感を得ることができます。帰属は単なる感情ではなく、日常生活で大切な役割を果たしているのです。それでは様々な帰属関係のバランスを取ることができないとき、または帰属の利点を活かすことができないときはどうでしょう?当社の参考文献のリストには、社会学研究から古典文学まで優れた書籍を紹介しています。帰属に関するこの側面について広い視野で深く考察することができます。
現代人は浅い帰属意識を簡単に感じることができる、という兆候が研究で見受けられています。同じような考えを持つ人々の存在を感じることはあっても、コミュニティの一員であると感じたり、それに積極的に貢献したりすることはあまりありません。TikTokのクリエイターやブランド広告主、政治活動家などとの浅い帰属関係を受動的に経験する機会は豊富に与えられているものの、深い帰属意識を持つことはますます難しくなっているのです。学校、自治体、教会のような伝統的な制度に関与しなくなると、生活における帰属意識や繋がりの源として、趣味や興味ある分野に関連する非公式のコミュニティに着目しがちです。しかし、こうした形態の帰属関係を最大限に活用することにも苦労しているというのが現状でしょう。帰属意識に関する当社のポッドキャストのエピソードでは、この現象をさらに掘り下げ、浅い帰属意識を重視することがいかに孤独感を助長しているのかを考察しています。
帰属を創る、壊す、疑問視する
帰属意識は、個人ではなく、他人とのやり取りの中で生じます。双方が持っている共通点を明らかにし、強調し、さらには拡大するという経験の中で発生するのです。帰属の可能性を感じるには、まず共通点を見つけることが大切です。帰属意識を感じ始めたら、他者と苦労や達成感を共有したり、過去の想い出を一緒に振り返ったりするなど、互いの共通点を強化する体験が必要になります。グループ全体のアイデンティティ形成やグループ内での役割に貢献していると感じる人ほど、強い帰属意識を感じることが研究で判明しました。コミュニティ内の個人と親密になることで、そのコミュニティ全体への帰属感を確信することもあります。そして興味深いことに、新しい経験やスキルの構築、共通点のさらなる発見などを通じ、相互の共通点が平行線ではなく進化することで帰属意識が高まることも明らかとなっています。ここで挙げたような状況が起きない(またはその頻度が十分でない)と帰属意識は深まりません。
反対に、共通の体験を通じて、受け入れられている、お互い様だ、似た者同士といった感覚が持てないと帰属関係は崩壊してしまいます。ブラジルから日本に移住した3家族を主題にした当社のドキュメンタリー映画「One Day We Arrived in Japan」が痛烈に描写しているように、自分たちが共有していると思っていた価値観、信念、アイデンティティ、規範の不一致が明らかになったとき、私たちは居場所を見失ってしまうのかもしれません。自分自身のある側面(アイデンティティ、性格、過去の体験)が受け入れられなかったとき、または相手から見返りを得ることができなかったとき、私たちは帰属意識を失うことがあります。
しかし、帰属関係のすべてが悪い結末というわけではありません。グループやコミュニティから必要なものを得て、その目的が達成されたら他に移動して所属するため、帰属意識を失うというケースもあります。時には、集団の一部の人たちと深い帰属意識を築いたり、または集団内の個人と関係を持ったり、必要なものを得たので一緒に集団を離脱するということもあるでしょう。また、すべての帰属が善良というわけでもありません。帰属には、集団思考、排除思考、または同調圧力を生みだす力があります。こうした誤った情報や画策が広まることで、グループの社会構造が崩壊することもあるでしょう。帰属意識は、カルトや宗教戦争、人種差別、テロなどの重大な要因となることが多々あります。
確かに、私たちは常に帰属を必要としているわけではないのかもしれません。例えば、コロナ禍でリモートワークやハイブリッドワークが登場して以来、職場に帰属する必要性(必要なら、どのような方法で?)の有無について疑問視されています。これは雇用主にとっては危機的状況です。リモートワーク、ハイブリッドワーク、ギグワークの時代に、オフィスや会社への帰属意識をどのように創出すればいいのでしょうか?一方、従業員にとって、これは啓示的または革命的な現象なのかもしれません。意義のある優れた仕事をこなす上で帰属意識を持つ必要があるのでしょうか?それとも職場での帰属意識は、割安に生産力を高める労働搾取の手段なのでしょうか?私生活と仕事に占めるべき帰属意識の最適な割合とは?
企業における帰属意識
企業や組織にとって帰属意識はとても重要です。帰属意識を上手く活用することで、ブランド、サービス、製品、空間と人々の間に繋がりが生まれることが分かっています。もちろん、帰属意識はこうしたエンゲージメントを高めますが、そこから実際の信頼関係を生み出すことも重要です。グループに属しているという感覚を与えるだけでは十分ではありません。様々のタイプの帰属関係が異なる役割を果たしており、コミュニティで深い帰属意識を生むには相手に応じた特定の体験や接点が必要となります。これについては、消費者の帰属意識を深めるためにブランドが利用できるツールを説明した記事「Can Hermès Be Your Friend?(エルメスは友達になれるか?)」で詳しく説明しています。
帰属関係のタイプ、メリット、得られる体験を理解することは、帰属意識を上手く活用する上で不可欠です。間違ったやり方をすると表面的で的外れと思われる恐れがあります。当社のインタビューシリーズである「How I Built Belonging(帰属意識を生み出す方法)」では、企業経営者やビジネスリーダーに「組織の中核的なビジョンや使命における帰属の役割とは?」「排他と不寛容‐組織や会社は誰のためのもので、現時点で考慮されていない人は?」といったビジネスにとって不可欠な疑問を経営者やビジネスリーダーに投げかけました。同シリーズでは、ルルレモン(lululemon)のニッキ・ニューバーガー氏、ハーモニー(HerMoney)のジーン・チャッツキー氏、テルトゥリア(Tertulia)のリンダ・ハメス氏、セサミワークショップ(Sesame Workshop)のキム・フォールズ氏とスコット・カメロン氏をお迎えし、組織が社員や消費者と帰属関係を生み出すための様々なアプローチについて議論しています。
特定のブランド、製品、サービス、空間において帰属関係を最適に実現する方法を把握していることも重要です。例えば、オンライン上で帰属関係を創出する方法は豊富にありますが、非常に深い帰属意識は、オンラインではなく現実世界で生まれるものなのかもしれません。また、直感的に違和感があるかもしれませんが、帰属意識は商取引で発生することもあります。帰属意識を持つためにマーケットプレイスやマイクロペイメント(少額決済)を利用している人もいるのです。他者と繋がる方法や生活に意味を持たせる手段が急速に変化を遂げる現状において、トレンドを追う以外に、日常生活で帰属関係がどのように発生しているのかを把握することが企業にとって重要なのです。
個人を集団に変える「帰属」という目に見えない構造づくりという難題に関心のあるすべての人にとって、私たちの知見、アイデア、声、画像が出発点やインスピレーションとなることを願っています。帰属意識の下に集まり、探求し、コミュニティを構築する方法を見い出しましょう。私たちの繋がりはここから始まります。